毎日、本当にお疲れ様です。「もう限界、逃げ出したい…」とトイレでため息をついていませんか?
「時短勤務は3歳まで」という壁を前にして、これ以上どう頑張ればいいのかと頭を抱えているあなた。
今まさに、心がパンクしそうな状況にいるのではないでしょうか。
私も40代の共働きワーママとして、同じようにしんどさを感じてきました。
法律で決まっているはずの時短勤務なのに、なぜか毎日時間に追われ、仕事は終わらず、家は荒れていく。
周りからは「時短でいいね」なんて言われるけれど、実際はキャパオーバー寸前。
「もう辞めたい」と感じる日も一度や二度ではありません。
しかも、3歳でこの支援が終わったら、どうやってフルタイムに戻るの?という不安。
その先には「小1の壁」も控えています。
「みんな一体どうしてるの?」と、出口のない不安に押しつぶされそうになることもありました。
でも、その「無理」は、あなたの頑張りが足りないせいでは絶対にありません。
この記事では、なぜ私たちがそう感じてしまうのか、その理由と構造をひも解きながら、この状況を乗り切るための具体的なヒントや、心を楽にするお助けアイテムを、同じワーママ目線でご紹介します。
- 「時短3歳まで無理」と感じる構造的な理由
- 2025年の法改正で何が変わるのか
- キャパオーバーから抜け出すための具体的な考え方
- 心を楽にするためのおすすめ時短グッズ
「時短3歳まで無理」と感じる構造的な理由

なぜこんなに「無理」だと感じてしまうのか。
その原因はあなたの根性ではなく、制度や職場の「構造」にありました。
まずはその正体を知ることで、心を少し軽くしましょう。
制度の限界?時短勤務と法律のポイント

「時短勤務」は、育児・介護休業法で定められた私たちの正当な権利です。
基本として、会社は3歳に満たない子を育てる従業員に、1日6時間の短時間勤務制度を設けなければならない「義務」があります。
(出典:厚生労働省「育児・介護休業法について」)
でも、問題はここから。
多くの会社の就業規則が、この法律の最低基準に合わせて「時短は3歳まで」となっていますよね。
だから3歳になった途端、「はい、明日からフルタイムね!」と崖から突き落とされるような気分になるんです。
「3歳になったら自動的にフルタイムに戻り、残業も普通にしなきゃいけない」と思い込んでいる方も多いのですが、実は法律はもう少し私たちを守ってくれています。
ここで見落としがちなのが、「時短」以外にも私たちを守る制度がすでにあることです。
3歳以降も使える「残業免除」の権利
「時短」が終わっても、「所定外労働の制限(残業免除)」という権利は、小学校入学前まで使えます。
これは「時短」とは全く別の制度。
3歳でフルタイムに戻ったとしても、「フルタイム勤務、ただし残業は一切なし」という働き方が法的に可能です。
これ、お迎え問題を解決する強力なカードですよね。
もちろん、職場の雰囲気的に「そんな権利、使いづらいよ…」という現実があるのも承知しています。
ですが、「法律上はそういう権利があるんだ」と知っておくだけでも、会社と交渉する際のお守りになります。
法律に関するご注意
この記事で紹介する法律や制度の情報は、2025年11月時点での一般的な情報提供を目的としています。
法改正の最新情報や、あなたの会社での具体的な適用状況・就業規則については、必ず厚生労働省の公式サイトや、お勤め先の人事・労務担当部署、または社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
キャパオーバーと「申し訳ない」の正体

時短勤務で一番つらいのって、「私だけ早く帰ってごめんなさい」という、あの罪悪感ではないでしょうか。
私自身、先に帰るときに「お先に失礼します…(ああ、あの仕事も残ってるのに…)」と、毎日心がすり減る思いでした。
でも、この「申し訳ない」という気持ちは、あなたのせいじゃありません。
それは、職場で起きている「しわ寄せ」という構造的な問題が引き起こす「症状」なんです。
「しわ寄せ」問題の構造
- 構造的な人材不足:そもそも人員が足りていない(1人時短を取っただけで回らなくなる)。
- 管理職の怠慢:上司が業務分担の見直しをせず、「現場の頑張り」で解決しようとしている。
- 事実上のハラスメント:「時短なのに仕事量が変わらない」「時短を考慮しない納期設定」がまかり通っている。
まじめで責任感が強い人ほど、「私が早く帰るからだ」と自分を責めてしまいます。
でも、それは違います。
悪いのは、その構造を放置している会社や管理体制なんです。
時短3歳まで 無理で、辞めたいと感じる時
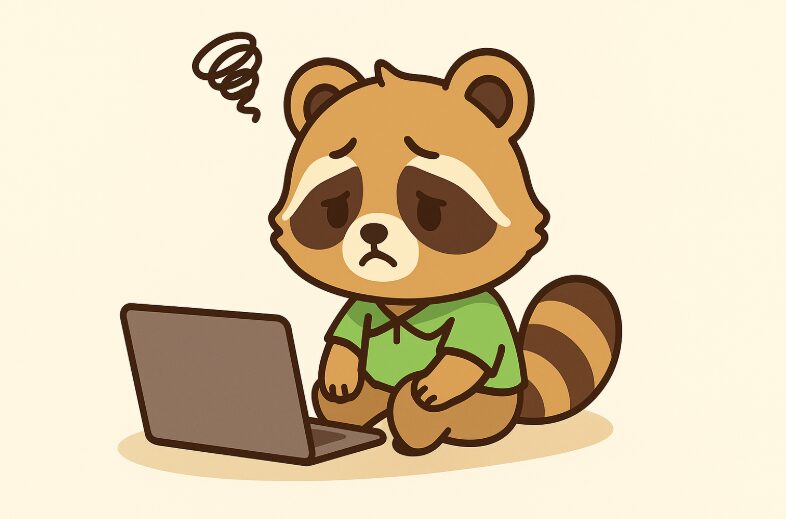
物理的なキャパオーバーと、さっきの「申し訳ない」という罪悪感に挟まれ続けると、当然「もう辞めたい」という思考が湧いてきます。
「仕事も中途半端、育児も中途半端、家事もできていない」
「周りのママは皆ハツラツとして見えるのに、私だけが疲れている」
こんなふうに自分を否定して、社会から孤立しているような孤独感に陥ってしまいます。
私自身、「こんなに無理して、キャリアも中途半端になって、何のために働いてるんだろう…」と何度も考えました。
でも、いざ辞めるとなると、家計のことや、一度キャリアを中断することへの不安も大きいですよね。
もし「辞めたい」理由が「今の働き方があまりにも辛すぎるから」だとしたら、辞める(ゼロにする)以外の選択肢がないか、一度立ち止まって考える必要があります。
もしかしたら、環境を少し変えるだけで「無理」が「なんとかなる」に変わるかもしれません。
3歳でフルタイムに戻るのは無理?

「3歳でフルタイムに戻るのは無理」。
私も心の底からそう思います。
さっき「残業免除の権利」があるとお伝えしましたが、現実は「権利はあるけど、使いづらい」というのが本音です。
フルタイムに戻る=「残業も当たり前」という職場の空気の中で、「私だけ残業しません」と宣言するのは、かなりの勇気が必要です。
「時短」という鎧が剥がされた瞬間、保育園のお迎え時間を気にしながら、終わらない業務と「帰れない」プレッシャーに板挟みになる…。
想像するだけで息が詰まります。
この「フルタイム復帰」という崖が、私たちを「辞めたい」という気持ちにさせる大きな原因になっています。
見落としがちな「小1の壁」という次の課題

「3歳の壁」をどう乗り越えるか必死に考えている今、本当に水を差すようで申し訳ないのですが、実はその先にはさらに大きな「小1の壁」が待っています。
これは、保育園時代より子どもの預け先確保や親の負担が増える問題です。
「時短3歳まで」の悩みと地続きになっている、次の大きな壁なんです。
「小1の壁」の主なギャップ
- 預かり時間の短縮(18時の壁): 保育園と違い、公立の学童は「18時まで」が基本。お迎えが間に合いません。
- 長期休暇と「弁当」の負担: 夏休み、冬休み、春休みなど、保育園時代にはなかった長期休暇が発生。学童は給食がないため、毎日の「弁当作り」が始まります。
- 親の活動の増加: PTAや平日の授業参観、旗振り当番など、学校に行く用事が急増します。
- 環境の変化: 子ども自身が新しい環境に馴染めず、不安定になることもあります。
つまり、「3歳の壁」を考えるときは、同時に「その先の小1の壁も見据えた働き方」をセットで考える必要があるんです。
3歳でフルタイムに戻れたとしても、小1でまた同じ(あるいはそれ以上)の壁にぶつかる可能性が高いのです。
実際、私も我が子は放課後の預かりに馴染めず1年の夏休み後に利用をやめました。
時短3歳まで 無理な状況への解決策リスト

では、この「無理」な状況をどう乗り越えるか。
根性論ではなく、具体的な「仕組み」と「考え方」、そして「心を楽にする買い物」のリストをご紹介します。
2025年法改正でどう変わる?

まず、私たちワーママにとって最大の朗報です。
この「3歳の壁」問題は国もやっと重い腰を上げ、2025年4月から法律(育児・介護休業法)が改正されます(一部は同年10月施行)。
一番のポイントは、「3歳から小学校就学前まで」の子どもを育てる従業員に対し、企業が「柔軟な働き方」の制度を導入することが「義務」になることです。
企業は、以下の選択肢から複数の制度を導入し、従業員が選べるようにしなければなりません。
企業に義務化される措置(例)
| 時短勤務制度の延長 | フレックスタイム制度 |
| テレワーク | 時差出勤 |
| 所定外労働の制限(残業免除) | 新たな休暇の付与(育児目的休暇など) |
これは強力な追い風です。
「うちの会社は3歳までだから」と諦めていた人も、今後は会社に対して「時短延長」や「テレワーク」の適用を交渉する明確な権利が持てるようになります。
自分の会社がどう対応するのか、今から人事部に確認してみるのは、将来の不安を減らすためにとても有効なアクションですよ。
時短勤務、みんなはどうしてる?

制度が整っても、日々の忙しさはなくなりません。
キャパオーバーを防ぐために、多くのワーママが実践しているのは「頑張らない」工夫です。
「共働きが上手くいく秘訣」として多くの人が挙げるのが、「完璧を目指さない」ことと「夫との分担」です。
データを見ても、「乗り越えた人」は「諦める勇気」を持っています。
- 「掃除なんて多少しなくても死なない」とおおらかな気持ちでいる。
- 夫の家事のやり方(洗濯物の干し方など)に口を出さず、やってもらった「結果」だけを受け入れる。
- 「察して」を捨て、やってほしいことは「業務連絡」として具体的に言葉で伝える。
「みんな、意外と手を抜いてるんだ」と知るだけで、心は少し楽になります。
「完璧な家事」より「ご機嫌な私」を優先する仲間は、たくさんいます。
「完璧な家事」をやめるシンプル術

心を楽にするための最もシンプルな力技は、「やめること」です。
私自身、家事が苦手なので、キャパオーバーを避けるために多くの「こだわり」をやめました。
あなたの時間と心は、「稼ぐこと」と「子どものケア」に使うべき最重要リソース。
家事は「家族が健康に生きていける最低限」で十分です。
やめることリスト
- 毎日の掃除機がけをやめる床掃除は毎週末でもいい。床掃除ロボを持っている方は、自分は「ロボが通れるように床の物を片付ける」ことだけをミッションにして床掃除を委託します。
- 料理の「レパートリー」を考えるのをやめる献立はパターン化しましょう。「月曜はカレー」「火曜は焼くだけの魚」「水曜はミールキット」など、考える脳の疲労を減らします。
- 「申し訳ない」と思うのをやめる時短はあなたの権利です。罪悪感を持つ必要はありません。堂々と休み、その分、勤務時間内は集中して成果を出すことに意識を向けましょう。子どもの発熱などでやむをえない場合もあります。その場合は相手の親切を忘れずに、自分が手伝える場合は進んで手伝う事が一番のお礼になりました。
- 「自分でなんでもやろう」をやめる夫、家電、外部サービス。頼れるものはすべて頼る。ワンオペで抱え込むことこそが、最大のリスクです。
心を回復させる「買い物ソリューション」

家事を「やめる」ために必要なのが、「心を回復させるための買い物」です。
これは単なる贅沢ではなく、あなたの時間と心の平穏を守るための「投資」です。
大きな家電だけでなく、日々の小さな「癒し」も重要です。
私の「お守り」的ソリューション
私が実践しているのは、「疲労困憊で倒れ込む場所(=寝室)」の質を上げることです。
質の良い枕やマットレス、お気に入りのアロマに投資すると、短い睡眠時間でも心の回復度が違います。
また、通勤時間を「自分のための時間」に変える、ワイヤレスイヤホンでのオーディオブック(読書)も、忙しい中で自分のメンタルを保つ大切な習慣です。
稼いだお金で「自分をご機嫌にする」小さなご褒美こそ、明日を乗り切る力になります。
おすすめ時短家電とミールキット

心を回復させるための具体的な「買い物リスト」です。
これらは、家事を「やめる」ための最強の武器になります。
1. ドラム式洗濯乾燥機
ワーママの三種の神器、その筆頭です。
「洗濯物を干す・取り込む」という作業がゼロになるインパクトは絶大です。
夜寝る前にセットすれば、朝には乾いた服が待っている。
この安心感は、何物にも代えがたいです。
「乾太くん」のようなガス乾燥機も強力な選択肢です。
ただ、お住まいの場所によっては洗濯機の稼働音が響いてご近所迷惑になる場合もあるので、早朝に回しても大丈夫な場所なのか、音の大きさなのかは確かめてから始めてください。
2. 食洗機(食器洗い乾燥機)
毎食後の「最後のひと仕事」から解放されます。
浮いた時間で子どもと絵本を読んだり、自分がソファでぼーっとしたり。
手荒れの悩みもなくなるのも嬉しいポイントです。
3. 電気圧力鍋・ホットクック
「火加減を見なくていい」というのは、想像以上にストレスフリーです。
朝、材料と調味料をセットしてボタンを押しておけば、帰宅時にはメインディッシュが完成しています。
カレーや煮物が格段に楽になります。
4. 食材宅配・ミールキット
「献立を考える」「買い物に行く」という2大ストレスから解放されます。
コープやパルシステム、ヨシケイ、Oisixなど、各社特色があります。
特に、カット済みの野菜と調味ダレがセットになった「ミールキット」は、帰宅後10分〜15分でまともな食事が完成するので、惣菜を買う罪悪感もなく、心の平穏を保てます。
オイシックスについては、スーパーで買えるミールキットをレビューしています。
【兼業主婦】オイシックスで「罪悪感」とキャパオーバーを解決!スーパー購入で気楽な時短術
「時短3歳まで無理」を乗り越えるヒント
「時短3歳まで無理」と感じるのは、あなたが一人で頑張りすぎているサインです。
法律(2025年改正)という追い風も吹いています。
会社の制度や夫との関係、そして便利な家電やサービス。
使えるものはすべて使い倒して、「完璧な母」ではなく「ご機嫌な私」でいることにも価値を見出してみてください。
あなたの働き方や生き方に「正解」は一つもありません。
あなたが笑顔でいられる方法が、あなたとご家族にとっての唯一の正解です。
この記事が、そのヒントになれば嬉しいです。



コメント