こんにちは。
常に洗濯物をした後は山を築き上げていたらくみです。
今はだいぶマシになりましたが、洗濯物の収納を楽にする方法はないかと常に模索しています。
仕事と子育てに追われる毎日、「洗濯 たたむ ハンガー 収納」と検索して、少しでも家事を楽にする方法を探していませんか?
洗濯物をたたむのって、本当に面倒ですよね。
ソファの上に乾いた洗濯物の山ができて、それを見るたびにため息…。
洗濯物をたたまない収納ができたら、どれだけ楽か。
Tシャツの首が伸びない干し方や、かさばるズボンの収納方法、クローゼットがパンパン問題など、悩みは尽きません。
子供服の細々とした管理も大変です。
この記事では、そんな悩みを抱えるあなたへ、私が実践してたどり着いた「たたむのをやめた」ハンガー収納の具体的なコツや、ニトリや無印、100均アイテムの活用法までお伝えします。
この記事を読んで、洗濯のストレスから解放されるヒントが見つかったら嬉しいです。
- 洗濯物を「たたむ」のをやめて楽になった理由
- 無印やIKEA、100均などハンガーの賢い選び方
- Tシャツや子供服の「たたまない」具体的な収納テクニック
- 泥汚れや体操服の「つけ置き」裏ワザ
究極の時短!私の洗濯はたたむのやめてハンガー収納術

毎日の洗濯、たたんで、しまって…本当に重労働ですよね。
私も以前は律儀に全部たたんでいたんですが、ある日「もう限界…!」と爆発しました。
そこから私の「たたまない」収納の研究が始まりました。
ここでは、私が「たたむ」を放棄してたどり着いた、ハンガー収納の基本と考え方をご紹介します。
洗濯をたたむのをやめた理由とストレスの変化

私が洗濯物をたたむのをやめた最大の理由は、「時間と心の余裕が欲しかった」からです。
もう、はっきり言って仕事と子育てで疲れ果てて、家事まで完璧にこなす気力なんて残っていませんでした。
乾いた洗濯物の山を見るたびに、「あぁ、あれをたたまないと…」と憂鬱になる。
そのストレスが本当に大きかったんです。
でも、思い切ってやめてみたらどうでしょう。
びっくりするほど誰も困らなかったんです。
夫も子供も、たたんであろうがハンガーにかかっていようが、着るものがあればそれでいい。
なんだ、私一人が「たたむべき」と思い込んでいただけだったんだ、と気づきました。
たたむ作業がゼロになったことで生まれた「時間の余裕」と、「やらなきゃ」というプレッシャーから解放された「心の余裕」。
これが私にとって一番大きな収穫でした。
無印・IKEA・ニトリ・100均ハンガーの選び方
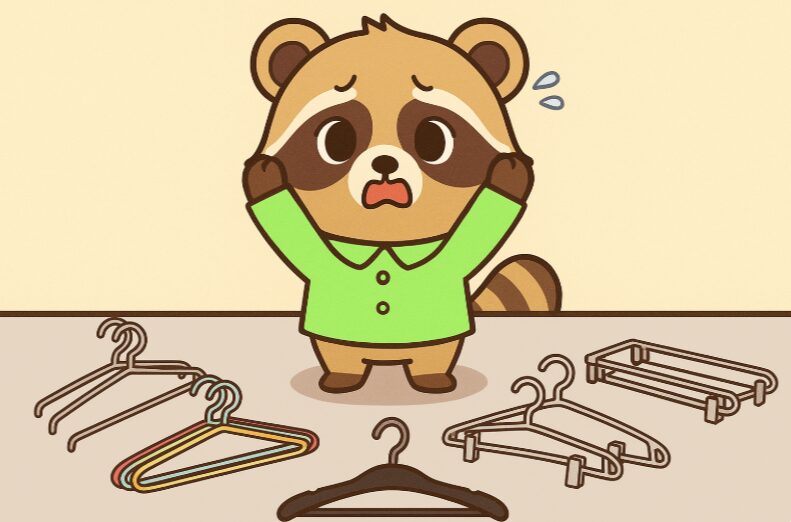
ハンガー収納に切り替えようと決めた時、次にぶつかるのが「どのハンガーを選ぶか」問題です。
ここで節約方向に走ると、後で「滑る!」「かさばる!」「服に跡がつく!」と三重苦になります(経験談です…)。
私は色々試した結果、大人の衣類は無印良品のアルミハンガー、子供服はIKEAの子供用ハンガーに落ち着きました。
なぜそれを選んだか、他のニトリや100均(ダイソー、セリアなど)のアイテムと比較してどうだったか、ポイントをまとめます。
大人の衣類:無印良品を選んだ理由
大人の服で重視したのは「統一感」「薄さ」「シンプルさ」です。
- 無印良品(アルミハンガー): とにかく薄くて軽い。クローゼットのバーにかけられる量が格段に増えます。デザインがシンプルで統一感が出るのもお気に入り。滑り落ちやすい素材(レーヨンとか)には向きませんが、私は干す時からこれを使っているので、そのままクローゼットに直行できています。
- ニトリ(滑らないアーチハンガー): これも人気ですよね。アーチ型でニットなどに跡がつきにくい点が高ポイントです。ただ、無印に比べると少し厚みがあるのと、滑らない加工(ベロアっぽい素材)が、服を手早く取りたい私には少しストレスでした。
- 100均(ステンレスハンガー): ダイソーなどにもあります。コスパは最強。ただ、モノによっては強度が少し不安だったり、無印のアルミの質感の方が好みだったので、私はメイン使いにはしませんでした。
子供服:IKEAを選んだ理由
子供服は「安さ」「軽さ」「サイズ感」が命です。
- IKEA(子供用ハンガー): カラフルで可愛いし、何より安い!そして結構硬い。子供服ってすぐサイズアウトするし、数も多いので、低コストで数を揃えられるのは本当に助かります。プラスチックで軽いので、子供が自分で出し入れする練習にもぴったりでした。個人的には乱暴に引っ張りがちな我が子が使っても壊れないのも良かったです。
- 100均(子供用ハンガー): セリアなどにも可愛いものがあります。ただ、IKEAの方が一度にまとまった数を買いやすかったので、私はIKEAで統一しました。
ハンガーを統一するだけで、クローゼットの中が見違えるほどスッキリして、インテリアのおしゃれ度が上がったと感じられました。
ハンガー収納Tシャツの伸び対策と干し方

「ハンガー収納にしたいけど、Tシャツやニットの首元が伸びるのが嫌」という悩み、すごくよくわかります。
私もそれが一番の懸念でした。
でも、これは「干し方」と「ハンガーの入れ方」で解決できます。
まず、衣類が濡れている時は重さで伸びやすいので、乾燥機である程度乾かしてからハンガーにかけるか、もしくは平干しネットを使うのが理想です。
でも、私の場合、全部は無理でした。
なので、「干す時」のハンガーの入れ方を徹底しています。
Tシャツの首を伸ばさないハンガーの入れ方
- ハンガーを首元から入れない!(絶対!)
- Tシャツの裾(胴体)の部分からハンガーを差し込みます。
- ハンガーの片方の肩を、首元を通って袖口に通します。
- もう片方の肩も袖口に通します。
これだけです。
このひと手間だけで、首元のリブがデローンと伸びるのを防げます。私はもう無意識でやっています。
ニット類に関しては、やはり自重で伸びやすいので、無印やニトリにあるような「アーチ型」のハンガーを使うか、滑らないハンガーに「折り掛け(二つ折りにして掛ける)」するのがおすすめです。
子供服の小物類はたたまない収納(カゴ)が正解

大人の服はハンガーで解決。でも、小さくてハンガーにかけられない子供の小物類…靴下やハンカチはどうするか?
答えはシンプルです。
「投げ込み」です。
私は楽天で買った子供部屋向けのカラーボックスを使っています。
それに、ダイソーで売っている長方形のカゴを組み合わせて入れているんです。
そして、カゴごとに「こっちは靴下」「こっちはハンカチと給食袋」みたいに、ざっくり分類しています。
(靴下はたまたまスペースが余っていたからですが…)
この収納を、そのまま子ども部屋に置いています。
特にハンカチと給食袋をまとめておくと、学校の準備をするときに子供が自分でできるので、すごく便利なんです。
我が子は、タンスやフタ付きのボックスみたいに中身が見えなくなると、その存在をすっかり忘れるタイプです。
だから、できるだけ「見える収納」にするのが、我が家流のルールとしました。
下着と靴下の「たたむ」最小化ルール

子供の靴下やハンカチは子供部屋のカゴに投げ込みですが、さすがに大人の下着や靴下、それと子供の肌着類までハンガーにかけるわけにはいきません。
こればっかりは「たたむ」というか「まとめる」作業が必要ですが、ここでもいかに楽するかを追求しています。
- 肌着・下着・大人の靴下: 100均(セリアやダイソー)で売っている「仕切りケース」を引き出しに入れて、そこに立てて収納しています。「たたむ」というより、丸めて入れてるだけとも言えます。もしくは適当に四角くして入れています。仕切りがあるので、倒れたりごちゃ混ぜになったりはしません。
- 靴下ハンガー(大人用): 話題になった100均の「ソックスハンガー」も使ってみました。靴下を履かせて、そのまま干して、そのまま収納できる…というアイテム。確かに画期的でしたが、ちょっと手間に感じたのと、洗濯機を乾燥機付きのものに変えたので、洗濯後は靴下を収納する引き出しに直行してます。靴下の迷子がなくなるので、合う人にはすごく良いアイテムだと思います。
たたむアイテムをこれだけに絞りましたが、ぐうたらな私はまだ若干疲労しています。
クローゼット直行ハンガーと種類

私がここまでお話ししてきた「ハンガー収納」のキモは、「洗濯物を干すハンガー」=「クローゼットに収納するハンガー」にすることです。
全自動洗濯機に変えても、どうしても乾燥にかけたくない素材の衣類はありますし。
そうした物は、洗濯物が乾いたら、物干し竿からハンガーごと外して、そのままクローゼットのバーにかけるだけにした方がずっと楽です。
これが「クローゼット直行ハンガー」です。
これにより、「洗濯物を取り込む」「たたむ」「(収納用ハンガーに)かけ直す」という3つの工程が一気に消滅します。
この運用をするために、ハンガーには以下の条件が求められます。
- 屋外でも(ある程度)耐えられる素材(ステンレス、アルミ、良質なプラスチックなど)
- クローゼット内でかさばらない「薄さ」
- 統一感(スッキリ見せるため)
だから私は、薄くて丈夫な無印のアルミハンガーをメインにしています。
私はボトムも無印を使っていますが、ズボンやスラックス類は、専用のスラックスハンガー(ニトリや山善などで売ってます)を使うと、省スペースになってシワも防げるのでおすすめです。
クローゼット直行ハンガーの種類(例)
| ハンガーの種類 | おすすめアイテム(例) | 特徴 |
|---|---|---|
| アルミ・ステンレス | 無印良品、100均(ダイソー) | 薄い、軽い、丈夫、錆びにくい。干す→収納に最適。 |
| 滑らないハンガー | ニトリ、MAWAハンガー | 服がずり落ちない。ニットやデリケート素材に。 |
| 子供用ハンガー | IKEA、西松屋、100均 | サイズが合う。安い。カラフル。 |
| スラックスハンガー | 山善、ニトリ、無印 | ズボンを複数かけられる。省スペース。 |
注意点:ハンガーの劣化
いくら丈夫な素材でも、直射日光に長時間当て続けると劣化は早まります。
特にプラスチック製は割れやすくなるので注意が必要です。
私は室内干しか、日が陰ってから外に出すようにしています。
洗濯、たたむ手間を省くハンガー収納と毎日の工夫

ハンガー収納という「仕組み」を整えたら、次はそれをスムーズに回すための「運用」の工夫です。
洗濯って「たたむ」以外にも、汚れ物を仕分けたり、干したり、取り込んだり…と地味な作業の連続でじわじわこちらの気力を削ってきます。
ここでは、仕組みを支える毎日の小さな工夫をお話しします。
泥汚れ・体操服の洗濯裏ワザ(つけ置き)

子供が持ち帰る、見るのも嫌な「泥汚れ」の体操服や靴下…。
こればっかりはハンガー収納以前の問題です。
泥汚れは、いきなり洗濯機で洗っても絶対に落ちません。
私の鉄板ルールは「つけ置き」です。
- まず、乾いた状態で泥をしっかり払い落とします。(濡らすと泥が繊維の奥に入り込むので乾いた状態で落とします。)
- バケツに40〜50℃くらいのお湯を入れ、洗濯洗剤(うちは粉末の「アタック高浸透リセットパワー」などを使ってます)を溶かします。
- そこに汚れた体操服を入れて、一晩つけ置きます。
- その後、軽くもみ洗いして、他の洗濯物と一緒に洗濯機で普通に洗います。
つけ置き洗いって汚れが浮き上がってきて楽ですよね。
汚れの程度によってはもみ洗い時にウタマロ石鹸も使っています。
洗濯ルーティンと時間帯のルール化

家事を楽にするには「何も考えずに体が動く」状態にするのが一番。
そのために「時間帯のルール化」は必須です。
私はこんな感じです。
- 夜(お風呂上がり): その日の洗濯物を洗濯機へ。タイマーをセットして回す。
- 朝(起床後): (もし乾燥機を使うなら)乾燥が終わっているので取り出す。または、夜のうちに干していたものをチェック。
- 朝(出勤前): 乾いた洗濯物をハンガーごとクローゼットへ移動。(所要時間5分)
ポイントは、「たたむ」作業がないので、朝の忙しい時間でも「しまう」まで完了できることです。
リビングに洗濯物が滞留する時間がゼロになりました。
乾燥機活用の罪悪感をなくす思考法

私、以前は「乾燥機=贅沢品、電気代がかかる、服が縮む」と思って、使うのにちょっと罪悪感がありました。
でも、今はガンガン使ってます。
考え方を変えて、「これは贅沢じゃなくて、私の時間と労力を買うための投資だ」と思うことにしました。
私が洗濯物を干して、取り込んで、たたむのにかかる時間(1日30分だとして)を時給換算したら?乾燥機の電気代なんて安いものじゃないか、と。
乾燥機を上手に使うコツ
- 全部を乾燥させない: タオル類、下着、靴下、パジャマなど、シワが気にならず縮みにくいものだけ乾燥機にかけます。
- シワが気になる服は: 大人の服(シャツやズボン)は、乾燥機にかけずにハンガーで干します。乾燥機にかける場合も、乾いたらすぐ(温かいうちに)取り出してハンガーにかけるとシワが伸びやすいです。
- 素材の確認: 服のタグを見て「タンブラー乾燥禁止」のマークがあるものは、絶対にやめましょう。
シワができるかどうかは、乾燥機の性能や詰め込み具合、そして何より「衣類の素材」が大きいです。
乾燥機とハンガー干し、適材適所で使い分けるのがいいやり方かなと思います。
洗濯を毎日する理由とメリット

「洗濯、まとめ洗いしてます」という方も多いですよね。
でも、私は断然「毎日洗う派」です。
なぜなら、「まとめ洗い」は一回あたりの片付け負担が重すぎるから。
乾燥機にかけない洗濯物がそこそこの量入った洗濯機。
そこから濡れて重くなった衣類を取り出す作業、あれが本当に嫌いで…。
なるべく乾燥機にかけても問題ない素材の衣類を買うようにしてはいます。
それでも、どうしても干さなきゃいけない物もちょこちょこ出てくるので、乾燥しない洗濯時ものはまとめても2日にしています。
干す場所も一気に必要になりますし。
毎日ちょこちょこ洗う方が、1回の量が少ないので、
- 洗濯機から取り出すのが楽。
- 干す(ハンガーにかける)のが数分で終わる。
- 乾くのが早い。
- (結果的に)すぐにクローゼットにしまえる。
という好循環が生まれます。
「たたまない収納」を実践するなら、溜め込まずに毎日回す方が、システム全体がスムーズに回る気がします。
洗濯はたたむを放棄。ハンガー収納が最適解
ここまで、私が実践している「たたまない」洗濯術をお話ししてきました。
結論として、私のような(家事が苦手で忙しい)タイプにとって、洗濯は「たたむ」を放棄し、ハンガー収納に切り替えるのが最適解でした。
もちろん、全ての衣類をハンガーにかける必要はありません。
ニットのように「たたむ」方が向いている服もありますし、下着や靴下はたたむ(まとめる)しかありません。
大切なのは、「すべてを完璧にたたまなくてもいい」と自分を許してあげること。
そして、「たたむ」と「ハンガー(かける・投げ込む)」のメリット・デメリットを理解して、自分のライフスタイルに合わせて使い分けることだと思います。
もし今、洗濯物の山にうんざりしているなら、まずは「Tシャツを1枚、ハンガーで干してそのままクローゼットにかける」ところから試してみませんか。
その小さな一歩が、あなたの家事ストレスを大きく減らしてくれるかもしれません。



コメント